こんにちは!
2人のやんちゃ女子を育てながら
お仕事を頑張るまおみと申しますʕ•ᴥ•ʔ
今日は私も頭を悩ませた「小1の壁」のお話です。
どもが小学校へ入学する――
それは親子にとって大きな節目となる瞬間です。
しかし、多くの保護者がこのタイミングで直面するのが、
「小1の壁」と呼ばれる問題です。

小1の壁?
初めて聞いた!!

私も去年この壁に悩まされたよ。
今日はそのお話を書いていくね!
悩んでる誰かのためになればと思います。
この「壁」とは、子どもが小学校に入学することで、
家庭や仕事、生活にさまざまな変化が生じ、
保護者がその対応に苦慮する状況のことを指します。
特に共働き世帯にとっては、
今まで当たり前だった保育園の延長保育や柔軟なサポートがなくなり、
日常のスケジュールを大きく見直す必要が出てきます。
「小1の壁」は、子どもの成長の一歩であると同時に、
保護者にとっても“次のステージ”へのチャレンジとも言えます。
この「小1の壁」とは一体何なのか、
どう乗り越えられるのかを、わかりやすく、
そして実際の声を交えながらご紹介していきます。
「自分だけが大変なのかな…?」と感じている方も、
きっと共感できる内容があるはずです。
少しでも不安が軽くなるようなヒントをお届けできればと思います。
「小1の壁」とは?その正体に迫る
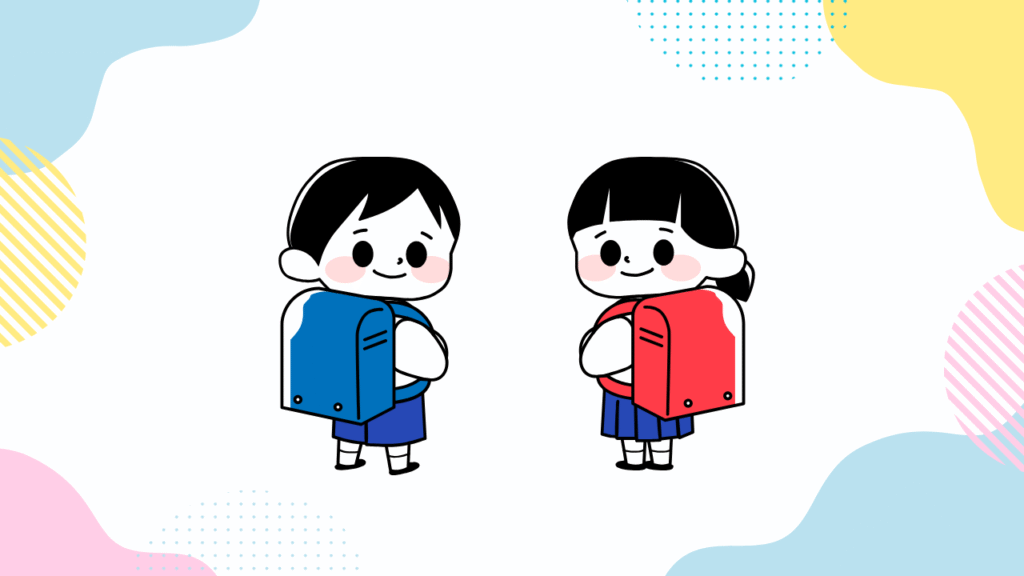
「小1の壁」という言葉は、特に共働き家庭でよく耳にされますが、
その実態は家庭ごと色々な違いがあると思います。
なぜ小学校入学が「壁」となるのか、
その背景を具体的に見ていきましょう。
保育園・幼稚園と小学校の違い
まず、大きな違いは学校の預かり時間です。
保育園や幼稚園では、早朝から夕方まで、
さらには延長保育などで柔軟に子どもを預かってくれる体制が整っています。
ですが小学校では授業が午後2時〜3時台には終了してしまいます。
結果として、子どもだけが早く帰宅する時間帯が生まれるのです。
この時間のギャップが、共働き家庭にとって最初の大きな「壁」となります。
特に小学1年生の最初の1週間は給食もなく、
11時ごろには途中まで迎えに行かなくてはいけない。
など大変なことも多いですよね…

確かに言われてみればそうだね!
フルタイムで仕事をしている人は大変そう。

そうなんだよね。
特に最初の1週間は子供も大人も慣れていないから
本当に大変。
春休みで崩れてしまったリズムを戻すのも…ね。
学童保育の限界
多くの家庭が利用するのが「学童保育」(放課後児童クラブ)です。
小学校終了後に子どもを預かってくれる心強い存在ではありますが、
利用できる時間や人数に制限があるのが現実です。
- 勤務形態によっては利用が難しい
- 定員オーバーで入れないケースも
- 夏休みなどの長期休暇中は朝から預けられるが、給食がなく弁当対応が必要
- 学校とは別施設の場合、子どもが移動しなければならないこともある
学童保育だけでは、保育園時代のようなフルカバーは難しいです。
子どもの自立と安全面の不安
小学生になると、自分で学校に行く・自分で帰ってくるという行動が増えます。
これまでは送迎されていた子どもが、自分の足で歩くという変化は、
成長の証でもあり、不安の種でもあります。
特に1年生は注意力もまだ未熟で、
交通ルールの理解や周囲の状況把握が十分ではないことも。
親にとっては、安全に通えるか・帰宅後はどう過ごしているのか。
が大きな心配となります。

大きなランドセルを背負って、
一生懸命登校下校している姿は愛らしいけど、
同じくらい心配なんだよね。
家庭で感じる変化とストレス
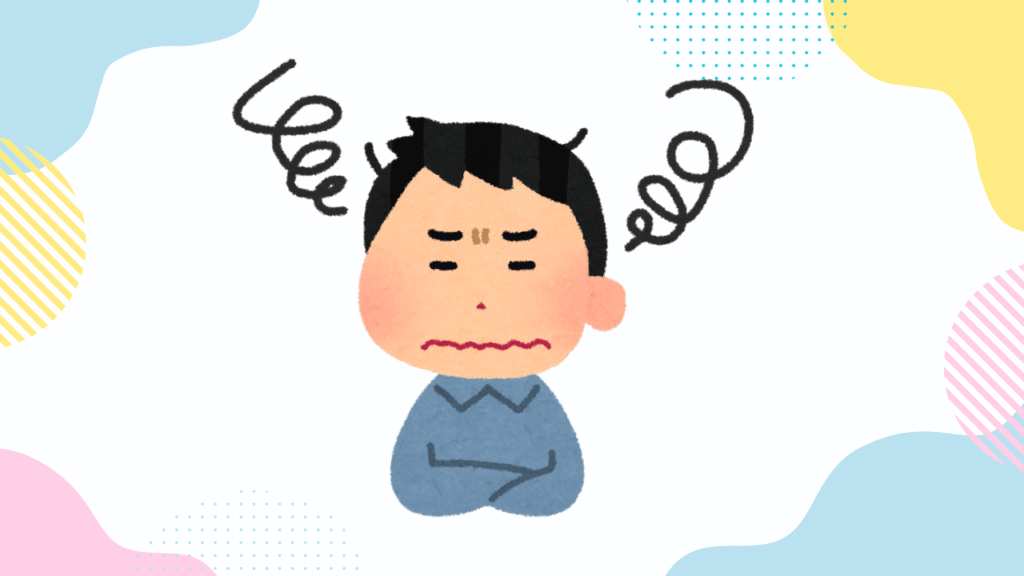
小学校入学は、子どもだけでなく家庭全体に大きな影響を与えます。
実際に家庭の中でどのような変化が起き、
どんなストレスを感じやすいのかを具体的に書いていきます。
子どもの生活リズムの変化
小学校に入学すると、保育園時代よりも「自由時間が増える」ことが多いです。
放課後は授業が終われば自宅に帰るだけ、
という日も多く、生活のリズムに変化が生じます。
- お昼寝の時間がなくなり、夜早く眠くなる
- 宿題という新たなタスクが加わる
- テレビやゲームの時間が増えがち
このような変化により、家庭での過ごし方や声かけの仕方も調整が必要になります。

授業を受けることも慣れてないもんね。
椅子にじっと座って先生のお話を聞くのは
ちょっと大変そうだもんね。

そうなんだよね。
学校で疲れて帰ってきて、やっと自分のやりたいことが
できるのに、宿題もあるから最初は本当に大変。
保護者の働き方への影響
これまでフルタイムで働いていた保護者の多くが、
「勤務時間の調整」「時短勤務」「在宅勤務の検討」などを迫られます。
- 学童に預けられない日は仕事を休まざるを得ない
- 急な体調不良や行事対応で早退・有休が必要
- 登下校の見守りのために出勤時間をずらす
このように、仕事と家庭の両立が一段と難しくなるのが「小1の壁」なのです。
職場への理解が得られないケースでは、
強いプレッシャーや罪悪感を感じる保護者も少なくありません。
親子のコミュニケーションの変化
入学によって、子どもは新しい環境・友だち・ルールに囲まれることになります。
そのため、子ども自身がストレスを抱えやすくなる時期でもあります。
- 「学校どうだった?」と聞いても「別に」と返される
- 宿題や持ち物管理で叱ることが増える
- 感情が不安定になる(すぐ泣く・怒る など)
保護者も日々の忙しさに追われ、つい感情的になってしまうことも。
これにより、親子間にすれ違いや緊張感が生まれることもあります。

どうしても子供のストレスは溜まるもの・・・
大人がグッと堪えればいいけど、
それも難しいことがあるから難しい。
実際の体験談から学ぶ「壁」の乗り越え方
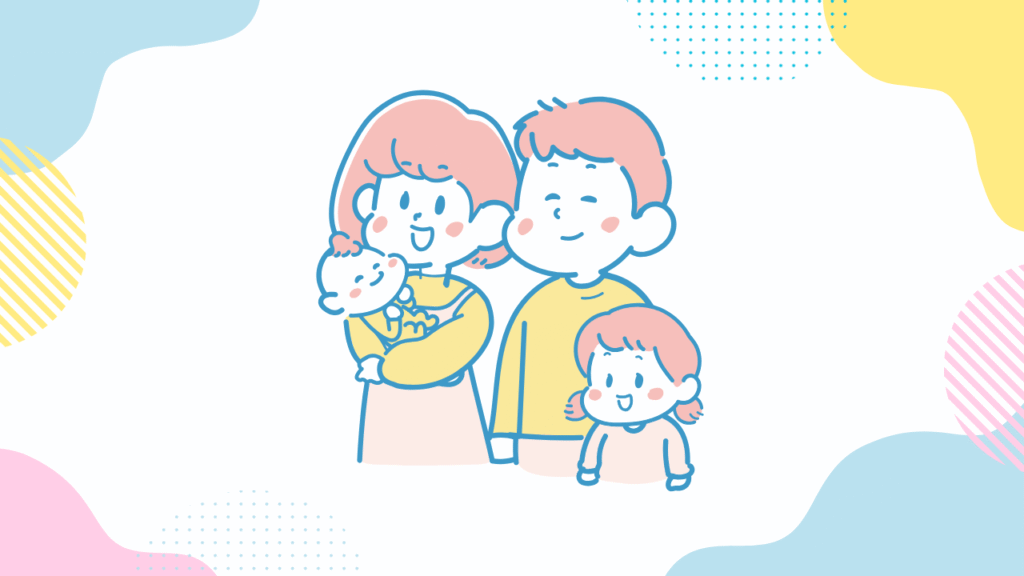
「小1の壁」は多くの家庭にとって共通の悩みですが、
その乗り越え方は家庭ごとに異なります。
実際の保護者の声をもとに、
どのように工夫しながら壁を乗り越えているのかを書いていきます。
ワーキングママの工夫:勤務スタイルを柔軟に
ケース:フルタイム勤務・共働きのAさん
Aさんは、子どもの小学校入学を機に、時差出勤制度を利用し、
朝は通常通り出社、夕方は早めに退社するスタイルに切り替えました。
また、在宅勤務日を週に1回設定することで、下校後の子どもと過ごす時間も確保。
「子どもが帰ってきたときに『おかえり』って言えるのが嬉しい。
自分も安心できるし、子どもも落ち着くみたいです。」
働き方を少し見直すことで、家族全体のストレスが減ったと言います。
子どもの自立を促す:スケジュールボードの導入
ケース:子どもが忘れ物が多いBさん家庭
Bさんの家庭では、学校の準備や宿題の管理が大変だったため、
「やることボード(To Doリスト)」を導入しました。
- 朝やること(着替え・持ち物確認)
- 帰宅後やること(手洗い・宿題・連絡帳確認)
ボードを使って子どもが自分でチェックできるようにすると、
親が毎回注意する必要が減り、子ども自身の自立心も育つようになったそうです。
「最初は一緒に確認していましたが、1ヶ月もすると子どもだけでやれるように!
“見える化”ってすごく効果的でした。」
「がんばりすぎない」選択:外部サービスを活用
ケース:子ども2人を育てるシングルマザーのCさん
Cさんは、学童がいっぱいで利用できず困っていた時に、
民間のキッズシッターサービスを検討。
最初は不安だったものの、試しに数回利用してみたところ、
子どももすぐに慣れ、今では週に数回利用する形に落ち着きました。
「全部一人で抱え込む必要はない。外のサービスを頼ることは、
手抜きじゃなくて“知恵”だと思っています。」
保護者が心に余裕を持つことが、家庭全体の安定につながります。
これらの体験談からわかるように、
「小1の壁」は一人ひとりが自分たちの生活スタイルに合った工夫を重ねることで、
少しずつ乗り越えていけるものです。
完璧を目指すのではなく、柔軟さと周囲への相談がカギになります。
行政や学校、地域の支援を活用する

「小1の壁」を乗り越えるために、家庭だけでなんとかしようとすると大きな負担がかかります。
だからこそ、行政や学校、地域が提供するサポートを上手に活用することが重要です。
具体的にどのような支援があるのか、どうやって使えばいいのかをご紹介します。
学童保育(放課後児童クラブ)
学童保育は、小学校1年生〜3年生を対象に、放課後に子どもを預かる制度です。
各自治体や学校、NPOなどが運営しており、子どもの安全な居場所として、
多くの家庭に利用されています。
【ポイント】
- 公立学童は市区町村が運営(利用申請が必要)
- 民間学童はサービス内容が充実している代わりに料金が高め
- 夏休みや冬休みなどの長期休暇にも対応(弁当が必要)
【活用のコツ】
- 早めの情報収集&申し込みが鍵(希望者多数の場合は抽選)
- 民間学童と併用する家庭も増加中
- 送迎サービス付きの学童もある(特に都市部)
地域の子育て支援サービス
自治体によっては、以下のような子育て家庭を支える制度を提供しているところもあります。
例:
- ファミリー・サポート・センター
→ 地域の登録サポーターが、子どもの送迎や預かりを手伝ってくれる制度 - 子育てひろば、親子サロン
→ 保護者同士の交流の場としても有効 - 子どもルーム(放課後子ども教室)
→ 放課後に学校の教室や体育館を使って、地域のボランティアが子どもと遊ぶ活動
【活用のコツ】
- 自治体のホームページや役所の子育て支援窓口で情報収集
- 一度登録しておくと、いざというときにすぐ頼れる
学校との連携・相談のすすめ
小学校には「学年主任や担任、スクールカウンセラー」など、
子どもと保護者をサポートするスタッフがいます。
困ったことがあれば、遠慮せず相談することが大切です。
相談内容の例:
- 宿題の取り組み方がわからない
- 子どもが学校での出来事を話さない
- 放課後の過ごし方に不安がある
「家庭でどこまで見ればいいのかわからない」という疑問も、担任に聞いてみることで解決することがよくあります。
学校は保護者の敵ではなく、チームの一員として一緒に子どもを育てる存在です。
小1の壁は「支援を知って、頼ること」から始まる
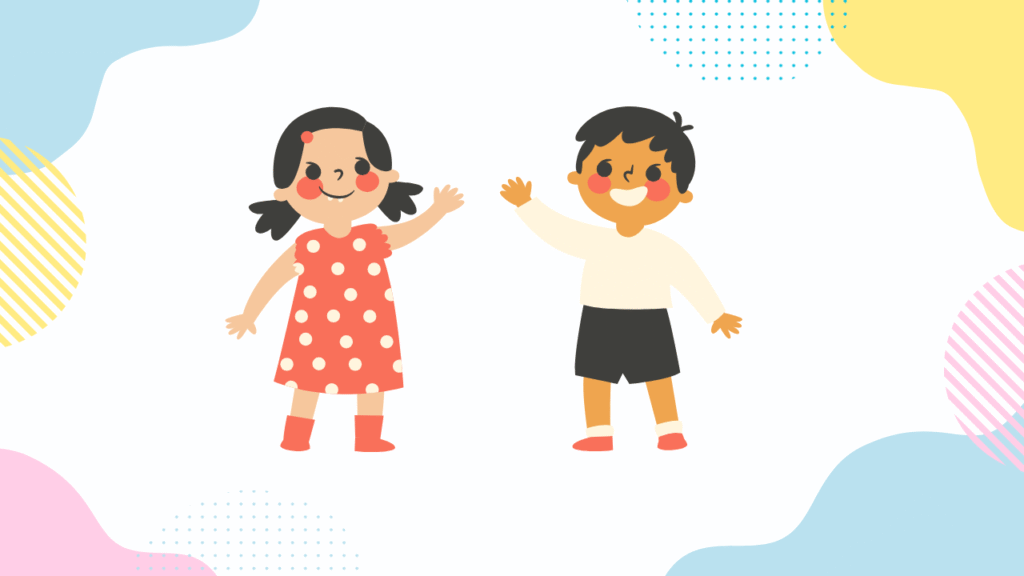
支援は“特別な人だけが使うもの”ではありません。
今や多くの家庭が何らかの制度を利用しながら日々を乗り越えています。
情報を集め、必要なときにためらわず頼ることが、
「小1の壁」攻略の大きな一歩です。
まとめ
小1の壁はお母さん・お父さんどちらか1人が
悩む問題ではありません。
家族全員で悩んで、外から助けを借りて解決するべき
問題です。
大人も子供も、どちらも楽しく生活ができることが
一番いいですよね!
そして、大人の機嫌がいいと子供も機嫌が良くなります。
不思議なことに。
もう少してゴールデンウィークです。
リズムが急激に変化しないように気をつけつつ、
楽しいゴールデンウィークにしてくださいね!
ご覧いただきありがとうございました!

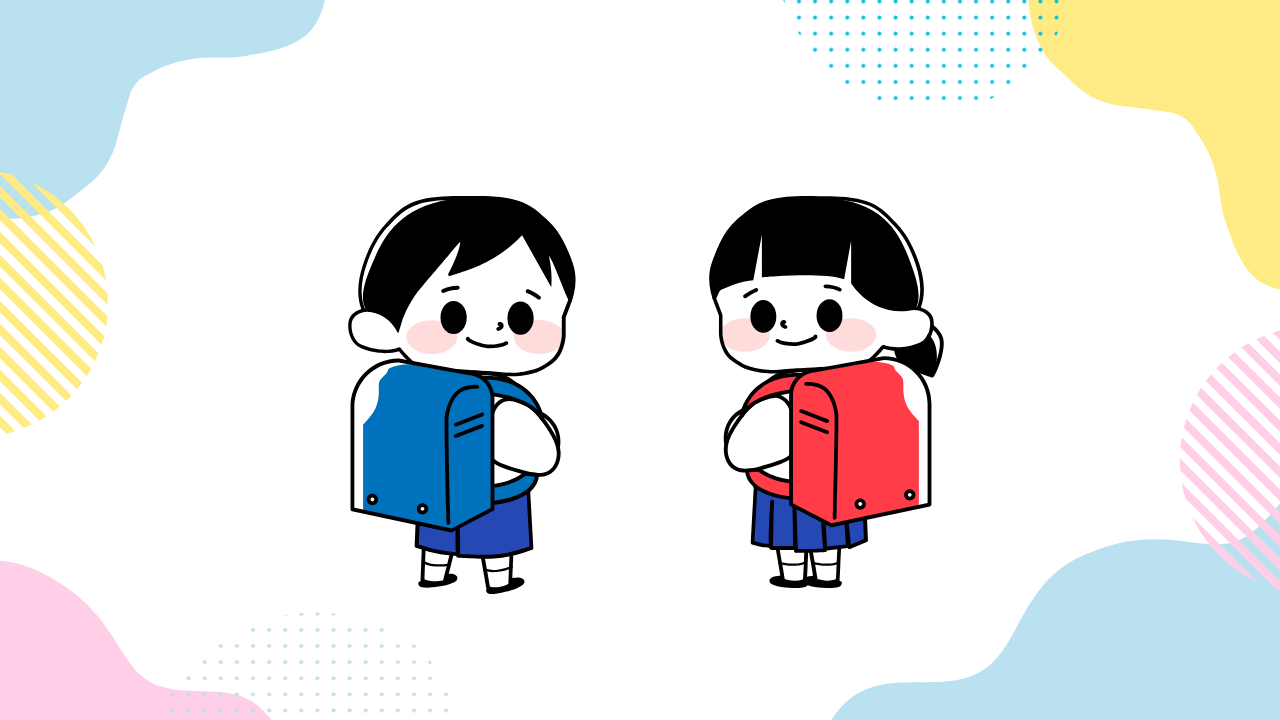


コメント